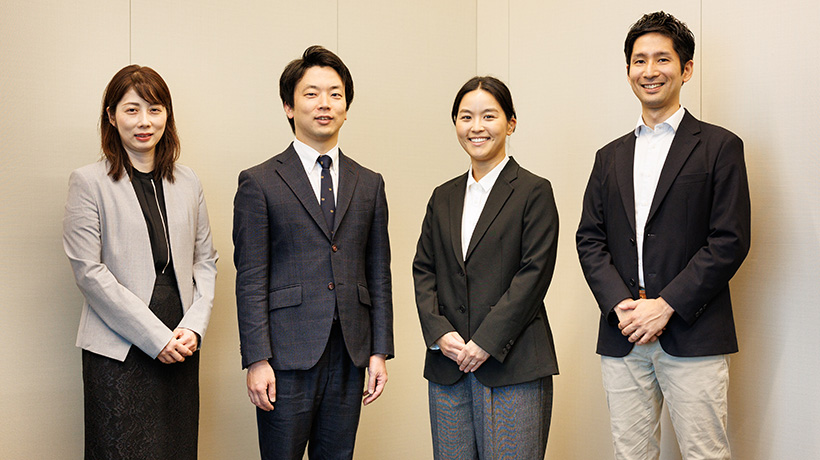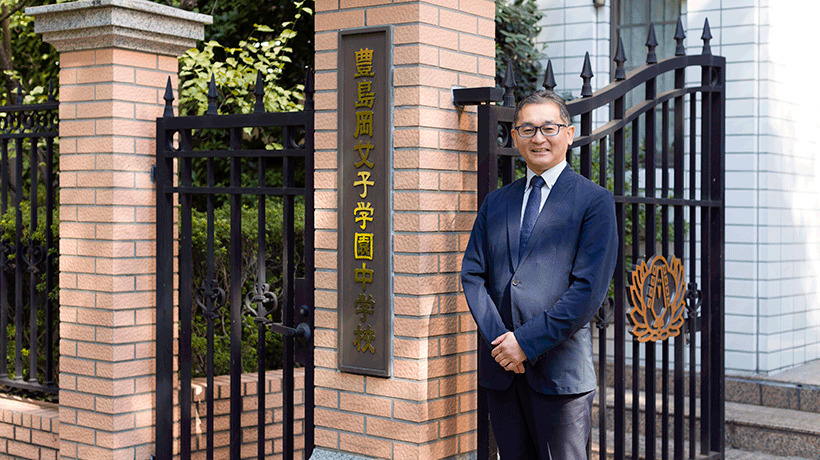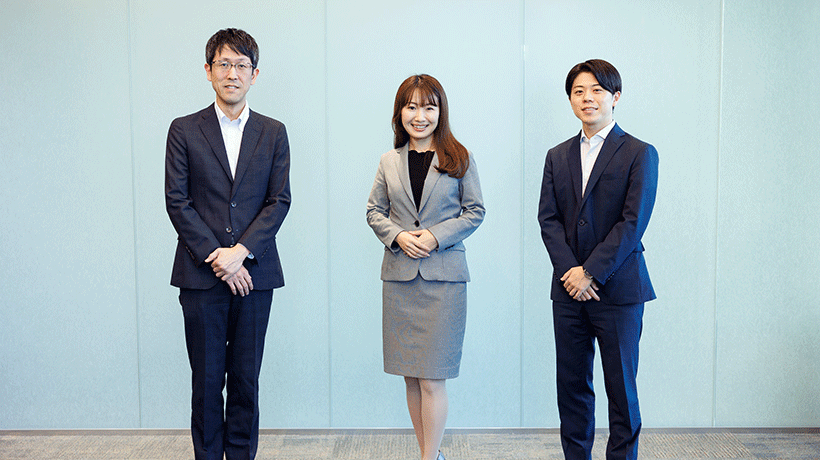ESG Stories
「自分は社会に何ができるか」を考える視座を与えてくれる
金融経済教育プログラム
2024年10月31日

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、「次世代」を重要なステークホルダーと位置付け、2014年以来、中学・高校生向けを中心に金融経済教育を実施してまいりました。 さらに、当社の理念に共感いただける複数の自治体や学校との「連携協定」締結を進めるとともに、学習指導要領の改訂に合わせた新たなプログラムを開発、小学生・大学生向けにも展開するなど、 金融経済教育の進化にも取り組んできました。今回は、2023年11月に新たに「連携協定」を締結し、新プログラム「お金の力-CHOICE-」※1を使った特別授業を実施した、 私立鷗友学園女子中学高等学校(東京都世田谷区)を訪ね、福井守明教頭にお話を伺いました。
実際の世の中の動きにマッチした金融教育を
採り入れることができるメリット
——貴校は、2023年11月、当社と金融経済教育に係る連携協定(以下、連携協定)を締結しました。連携協定締結までの経緯をお聞かせください。
当校では、中学3年の「総合的な学習の時間」の探求活動の中で職場訪問を実施しています。昨年(2023年)7月の職場訪問では、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(以下、MUMSS)
にお勤めの保護者の方にご協力をいただき、生徒12名が本社を訪問させていただきました。当日、生徒たちは、ディーリングルーム見学や社員の方々との座談会、「株の力」※2の短縮版を用いた学習などを体験しました。
後日、当校の生徒が非常に主体的に金融について学ぼうとしていたということで、「1回の職場訪問で終わらせてしまうのは惜しいので、金融経済教育を継続して行いませんか」とのご提案をいただきました。それが、連携協定締結のきっかけです。
その後の話し合いの中で当校の考え方に真剣に耳を傾けてくださって、「どういうことをやりたいのか、言ってほしい」とおっしゃってくださいました。
当校では、生徒に「学び続ける」人材であって欲しいと考えています。そのため「大学」「社会」へのトランジションを強く意識したカリキュラムを構築しています。
その一つとして文系、理系の区別なく、高校3年の必修科目として「政治・経済」の授業を行っています。そして、特徴的なこととして「政治」と「経済」を分け、
オリジナルのテキストを使い、別々の教員が授業を担当しています。当校では、その中でも金融を含めた経済の学習を非常に大事だと考えていて、
実際の社会の動きにマッチした金融経済教育を採り入れることができるのであれば、大変ありがたいことだと考えました。
一方で私たちは、MUMSSの金融経済教育に対する考え方をよく聞き、プログラム内容が当校の考え方に合致するものなのかどうかも検討しました。
「よりよく生きていくことについて主体的に考える力を育成する」ことをめざしているという点、プログラムが「探究活動に資する」内容である点は、まさに当校の考え方に合致するものであり、連携協定締結に至りました。
寄付をする、投資をするとはどういうことなのか、
生徒たちに強く響くものがあった
——連携協定を結んだ直後に、金融経済教育の「特別授業」を実施されていらっしゃいます。その特別授業は、どのようなものだったのですか。

連携協定を結んだ翌月の2023年12月、さっそく、「お金の力ーCHOICEー」を使った特別授業を実施しました。この特別授業は、高校1年と2年を対象に30人の定員で参加希望者を募集したのですが、
非常に希望者が多く、参加者は抽選で決めなければなりませんでした。
「お金の力-CHOICE-」は、5人ずつ5グループに分かれ、人口100人程度の架空の島の住人になってカードゲーム形式でお金の使い方を疑似体験していきます。各グループは「買う・貯める・増やす・譲る」
という4つのお金の使い方を通じて、「預金額・モノの充実度・心の充実度」という3つのパラメーターを変化させ、与えられたそれぞれの目標の達成を目指すというものです。
ここまでは普通のカードゲームとあまり変わりありませんが、「お金の力-CHOICE-」には島全体の状態を表す「経済・環境・社会」という3つのパラメーターがあって、
島全体の利害と自分たちの利害が衝突する場面が出てきます。そのとき、どういう判断をするのかが問われるわけです。とてもおもしろいですし、よく考えられた内容になっていると思います。
——どのような狙いから「お金の力-CHOICE-」を使った特別授業を実施したのでしょうか。また、特別授業に参加した生徒には、どのような影響がありましたか。
この特別授業の参加者を募集するとき生徒たちに呼びかけたのが、「『エリート』という考え方をちゃんと持とう」ということでした。本来、「エリート」とは「神から選ばれた」という概念を含むもので、
自分に与えられた環境や能力を生かし、持てる力を社会のために使っていく者が“真のエリート”なのです。
私たちは、日本に暮らしていることも含め、恵まれた環境の中にいます。その恵まれた環境の中にあって、自分たちはどういう力を社会のために使っていくのか、何を持って社会を動かしていこうとするのか。
そうした視座を、生徒たちに持ってほしかったのです。
もうひとつ、正解のない問いに、生徒たちをチャレンジさせたいという思いもありました。実際、昨年12月の「お金の力-CHOICE-」では、こんなことがありました。
ゲームの最終ターンで、偶然にも、自分の企業の利益を優先すれば目標達成になるけれども島全体のパラメーターを大きく下げてしまうという局面が生まれたのです。
まさに、正解のない問いかけです。そのグループは「譲る=寄付」を選択しました。そのとき、周りから思わず歓声があがっていましたね。
生徒たちに、寄付をするということ、時代の先を読んで投資するということがどういうことなのか、強く響くものがあったのではないでしょうか。
あの局面で考えたことは、確実に、生徒たちの力になっていると思います。
特別授業の感想を生徒たちに書いてもらったものを読んでも、「寄付や投資も、お金の使い方の一つとして考慮したいと思った」とか、
「自分がお金を使った後の社会への影響も考える必要があることを痛感した」とか、自分が使った先のお金の流れ方や、そのことが社会全体に与える影響など、
これまで想像していなかった領域に考えを広げていることがわかります。
学校だけではできないような学びの機会を、MUMSSの助けをいただいて生徒たちに提供できたことは、非常に良かったと思っています。
ワクワクするようなケミストリーを起こすことができないか
——貴校のこれからの金融経済教育に関して、当社にどのようなことを期待していますか。

当校は、学びを大学につなげ、社会につなげていくことを重視して学習指導を行っています。その中で、生徒たちに社会のことをいろいろと見させたいという思いが強くあります。
MUMSSの経済金融教育のプログラムは、主体的・能動的に取り組める内容であり、生徒たちに「自分と社会はつながっている」という視座を与えてくれます。
その貴重な学びの機会である「お金の力-CHOICE-」を使った特別授業は、継続して実施していきたいと考えています。
「お金の力-CHOICE-」にとどまらず、今後、さまざまな連携の形を実現させたいと考えています。その一つとして、大学受験に必要かどうか、
文系か理系かといった枠を取り払ったところで、「金融」がどういう世界なのかを生徒に伝えていく機会を大事にしたいと思っています。
例えば将来の職業選択を考えたとき、「金融工学」という領域があるように、金融業界は理系も活躍できる業界です。そこで、理系の女性社員の方に講演をお願いできませんかなど、いろいろと話をさせていただいています。
今できていないことを、やってみる。気付いていない視点を、提示する。そうしたワクワクするようなケミストリーを起こすことができるのではないかと、これからの連携の発展に期待しているところです。
※1「お金の力-CHOICE-」とは
学習指導要領の改訂に合わせて新たに開発された高校生向け金融経済教育プログラムで、2023年度から提供を開始した。「買う」「貯める」「増やす」「譲る」という4つの選択肢を手掛かりに、
自分のお金の使い方を考えるプログラム。自分のお金の使い方による自分の人生と未来の社会に対する影響を、ゲームを通して体験的に学ぶことができる。
※2「株の力」とは
2014年度から提供している、中高生向け金融経済教育プログラム。生徒たちは当社のインターンになったつもりで、「起業家」「投資家」「社会」という3つの視点から株式の仕組みなどを
グループワークで学び、その成果を「株の力」を伝える新聞広告として表現する。
【学校情報】
鷗友学園女子中学高等学校
1935(昭和10)年、創立。キリスト教の精神を基盤に「慈愛(あい)と誠実(まこと)と創造」を校訓とする、私立の中高一貫校。キリスト教精神・キリスト教的自由主義に基づく、 全人教育・リベラルアーツとグローバル教育を重視したカリキュラムを特色とし、「よろこび」と「真剣さ」あふれる学園を目指している。

講師経験者より:名古屋支店
中野 翼
2回の中学校訪問で
生徒の皆さんの成長を感じられたのは素晴らしい体験
学生時代、小中学生のサッカーのコーチをやっていた経験がありましたので、中学生に向けての「株の力」プログラムの講師役は楽しみにしていました。
事前の準備として講師を務めるための研修を受けるのですが、そこでテキストを見て、掲載事例を中学生にとって身近な事例に入れ替えるなど、分かりやすくより興味を持ってもらえる内容となるよう、
授業の準備を進めました。
実際の授業で一番大事に考えたのは、講師である自分に生徒の注目を集めること、私の話を集中して聞いてもらうことでした。ですから当日は着ていく服にも気を遣い、夏の暑い日だったのですが、
スーツとネクタイで臨みました。
自分の中学時代を思い起こしたとき、そもそも中学生って、お金の話は自らしないと思うんです。案の定生徒たちも、初めはお金の話をすることをためらっているように感じました。
しかし、教室の空気がやわらいでくると、活発に発言する生徒も出てきて、私が予想していたよりも活発に意見交換が行われる授業になっていきました。
「株の力」プログラムは5回の授業で成り立っており、そのうちの3回を2日に分けて当社の社員が担当します。2度目に同じクラスを訪ねたときの生徒からの質問や発言は、
1回目の授業とはまるで違うものでした。間に挟んだ数日間で学習したことの効果もあると思いますが、生徒たちが、お金や株式、経済の仕組みに対してしっかりとした意見を持ち、
堂々と話すようになっていました。たった2日間の経験ではありますが、自分が講師を務めた生徒の皆さんの成長を感じることができたのは、素晴らしい体験でした。
中高生の皆さんには、このプログラムを通じて、金融経済の仕組みをリアルに感じるとともに、今後の自身の成長やキャリア形成に活かしながら、これからの日本を牽引する人材をめざしていただけると嬉しく思います。
関連記事