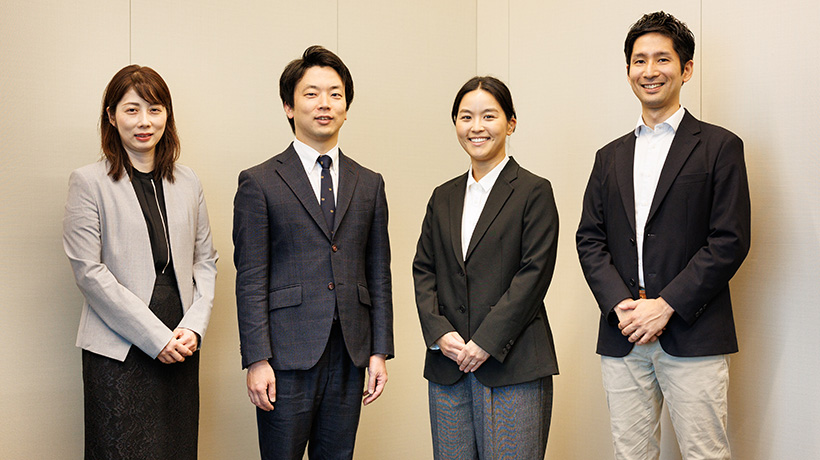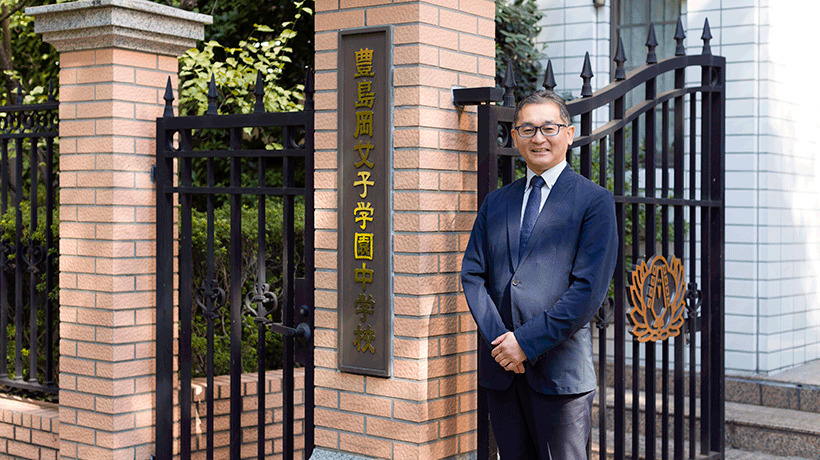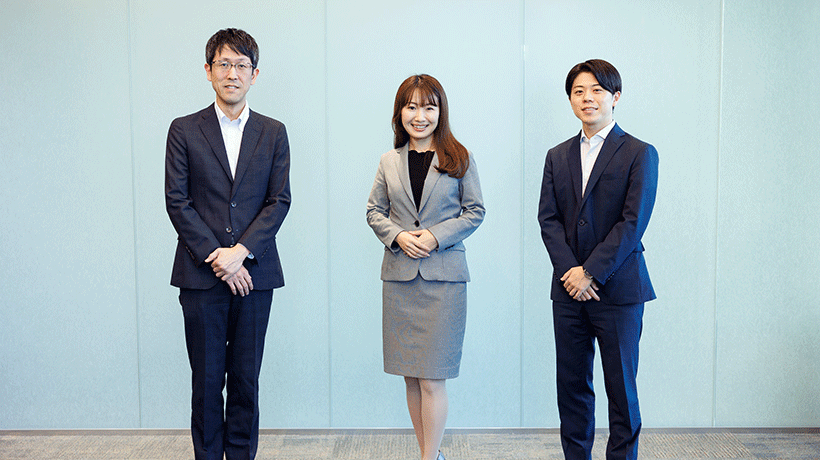ESG Stories
ESGを“自分ごと”にしていなければ、
お客さまとのエンゲージメントはできない
2024年12月27日

国際的なカーボンクレジットの先駆的な取り組みをはじめ、日本国内のサステナブルファイナンスの議論をけん引してきた
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの吉高まり氏に、「ESGといえばMUMSS」※ の実現に向けた施策について評価していただきました。
併せて、当社の社員ネットワークによるESGマインド向上のための新しい活動についても紹介します。
※MUMSS:「Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities」の略称
日本でも、ようやく「社会課題解決」が
金融の主流のテーマになってきた
「ESG」という考え方は、2006年に国連が提唱した「責任投資原則(PRI)」から生まれました。 その後、ESGが世界的な潮流になっていったのは、2010年代初頭のことです。リーマンショック後の金融当局による政策見直しの中で、 「環境問題も人権問題も資本市場にとってリスク要因であり、もっときちんと見ていくべきだ」という議論が起き、 まず欧米各国でESGが浸透していったというのが、大まかな流れです。 私は2000年に東京三菱証券(当時)に入社して以来、一貫して「環境」と「金融」を結びつける仕事に携わってきましたが、 ESGの考え方が定着していく中で、日本でもようやく「社会課題の解決」というテーマが金融の主流になってきたと感じています。

2024年1月から新NISAがスタートして、個人の投資が伸びていく環境になっています。 その中で、証券会社がもっとアクティブに動いていかなければならないと思います。 なぜなら、各企業の長期的な考え方を個人投資家の方々に説明するのは、証券会社だからです。 株式投資ですから、リスクもありますし、株価が下がることもあります。 もちろんそのことをお伝えしなければなりませんが、そうしたことだけでなく、 長い目で見ればESGやサステナビリティの視点が重要だということを、お客さまにわかっていただく必要があると思っています。 短期的な思考で株価を見るのではなく、企業の持続可能性を考慮し、財務以外の情報にも注意を払うことが主流になっていかないと、 これからの日本の経済はよくなっていかないのではないかと考えています。
社員へのエンゲージメントが大事なのは、
社員の先にお客さまがいるから
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(以下MUMSS)がESGの取り組みを進める中で、社員とのエンゲージメント、
役職員の「ESGスペシャリスト化」に特に力を入れていることは、とても大事なことだと思います。なぜ大事かというと、
社員の先に市場があり、お客さまがいらっしゃるからです。
市場とのエンゲージメントは、社員がESGを理解していなければ実現できません。
まず、社員とエンゲージメントしていく必要があるのです。企業の価値について中長期の視点でポジティブなインパクトを
いかに評価するかというときに、それに関わる証券会社として、ESGの意義が自分の中で腑に落ちていなければ、
お客さまとエンゲージメントできるはずがありません。
例えば、今はESGが主流になっているけれども、この先、反ESGのような動きが出てくるかもしれない。
そのとき、本当に何が大事なのかが“自分ごと”になっていれば、その先の見通しを説明できるはずです。
それをきちんと説明できるような社員になっていないと、市場を変えていけないと思います。
社員一人ひとりとのエンゲージメントをなおざりにしておくと、市場の変化、時代の変化に取り残され、
投資家から信用されなくなってしまうでしょう。
今、日本企業の価値が、海外からも評価されるような地合いになっています。
コロナ禍からの回復が早く、リスク管理もきちんとしていて、透明性が高い、
といった評価です。これを一過性のものではなく当たり前のことにするために、
投資家と市場の対話を手助けするスペシャリストが求められています。
そうしたエンゲージメントのスペシャリストが、
日本の資本市場をより良い方向へ変えていくのだと思います。
その意味で、ESGスペシャリスト化の取り組みに期待しています。
ESG感度が高く長期的視点に立った、
新たな個人投資を推進してほしい

私は、2024年5月、社員の皆さん主導でESGを推進するネットワーク「Employee Sustainability Forum(ESF)」に招かれ、講義を行いました。
そこで若い社員の皆さんに一番伝えたかったのは、「ESGを〝自分ごと化〟してほしい。そして、そのために現場感を持ってほしい」ということでした。
これは経験に基づく私の実感ですが、相手の立場に立って共感を持つことができないと、何を言ってもお客さまには響きません。
なぜ今、気候変動なのか、人権なのか。それらの社会課題について現場感を持っていないと、お客さまとエンゲージメントできないと思います。
いくらESG商品が充実していても、お客さまには手に取っていただけないでしょう。
大事なことは、他者に共感を寄せる経験を通じて、自分自身が気付きや認識を獲得することです。
このESFメンバーを対象としたESG学習プログラムには、
事業会社3社の視察が組み込まれていました。
社会の課題、環境の課題、さらに、課題解決のための資金がどう回っているかについて学び、
“自分ごと”にできる貴重な機会だったと思います。
ESFに参加した皆さんとは、講義に出向いた後さまざまにやりとりしていたのですが、
互いに切磋琢磨し、だんだんと熱が上がっていくのを感じていました。
5カ月間のプログラムでしたが、学びの期間を通じて皆さんは大きく成長されたと思います。
次のステップは、ESFに参加した皆さんが、その熱を社内でどう伝播していくかです。
ESGの感度を上げた社員が実行を通して周囲の人たちの感度を上げていく、
その連鎖によって、みんなのESGマインドが向上していくことを願っています。
繰り返しになりますが、証券会社の皆さんの先には、お客さまがいます。
証券会社の感度が上がることで、個人投資家の方々のESG感度を上げることができます。
例えば、若い世代の人たちがこれから資産形成をしていこうというときに、短期的な株価の変動に気を取られるのではなく、
もっと長期的な視点に立った、E(環境)も、S(社会)も、G(ガバナンス)も考慮する、
新たな個人投資を、MUMSSにはぜひ推進してほしいと思います。
最後に、もう一点、「女性の力」について触れたいと思います。私が入社した2000年当時、証券会社はエコファンドを販売していましたが、
そのエコファンドに最も関心を示し、ご購入いただいたのは高学歴の主婦層でした。あの頃は女性の社会参加が今ほどは進んでおらず、
エコファンドを買うことによって、間接的に社会に関わろうとしたのだと思います。やはり、女性は「次世代を育てる」という視点から、
環境や社会課題に対する感度が高いんですね。ですから、私は女性にとても期待しています。
男性が市場での勝ち負けを気にする傾向が強いのに対し、女性は、社会に対するインパクトとして投資を考える傾向があります。
女性の力をうまく引き出し、女性投資家を増やしていくという視点も重要だと思っています。
ESGに関する理解の深化や意識向上に加え、サステナビリティ人材の育成を中心としたすそ野拡大をめざし、 社員が主導する形でESGを推進するネットワークが「Employee Sustainability Forum(ESF)」です。 ESFでは2024年度上期に、サステナビリティやサーキュラーエコノミーについての講義や企業視察等を行う 5カ月間のプログラムを実施しました。 その成果として、参加メンバーはESG施策提言を作成し、2024年9月に経営陣に手渡しています。
ESFメンバーより:

私たち社員が「ESGといえばMUMSS」を体現できてこそ
お客さまに社会的存在意義を認めてもらえる
吉高フェローによるESGの本質、ESGの実情を捉えた導入講義は、「証券会社として提供できる価値とは、
どのようなものか」を改めて考えるきっかけと、その後の学習に取り組む強い動機付けとなりました。
学習期間の後半には、他企業の視察が組み込まれていました。見学させていただいた各社とも、
ESG活動を自然に取り込める仕組みができており、当たり前のようにESGに取り組む企業風土が構築されていたことが印象的でした。
社員一人ひとりの行動や意識にESGを浸透させ、そこをベースにした「ESGといえばMUMSS」が体現できてこそ、
お客さまから「MUMSSは社会的に存在意義のある企業体だ」と認めていただけるのだと思います。
「ESGの浸透に向けた仕組み」をつくり、「ESGの自分ごと化」を浸透させていくために、
これからもESFメンバーとして積極的に活動していきたいと思っています。
我々が起点となり社内に新たなムーブメントを起こしていきたい
プログラム受講に留まらず、まずは一緒に仕事をする同僚がESGを「自分ごと」として意識できるよう、
自ら考えた施策を推進するESGファシリテーターとして活躍していきたいと意識するようになりました。
サステナビリティに関する取り組みをより自発的に行える文化を当社に根付かせることができれば、
社員一人ひとりに自信が芽生え、やりがいと活力みなぎる職場へと変革し、社員エンゲージメントの向上にも
つながってゆくと信じています。ESFが実行する取り組みを通じて社員エンゲージメントが向上することは、
我々の活動の自信にもつながります。我々が起点となり新たなムーブメントを起こしていきたいと考えています。
プログラムを通じて強く感じたのは「社員とのエンゲージメントを高めること」が、企業のサステナビリティを向上させ、
お客さま、社会に波及していくのではないかということです。当社の革新的な取り組みが新たな価値を創造し、
その価値をお客さまや社会に認めていただくことで、当社の社会的存在価値が向上し、1st CALLをいただける
証券会社になることができると思っています。
関連記事